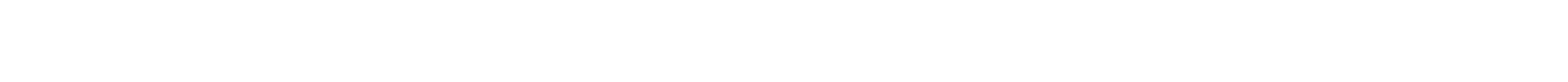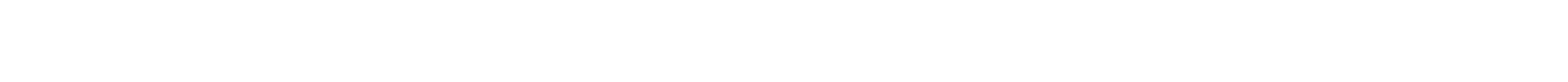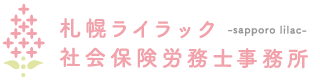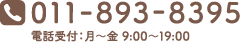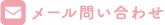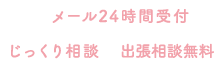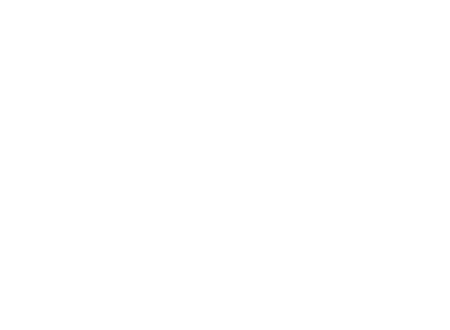障害者の生活保障をサポート!障害年金の基礎知識
視覚障害・聴覚障害・肢体不自由身体に関わる障害・精神障害・がん・糖尿病など病気にかかり長期治療が必要な方もいます。そのような場合、日常生活や就労を制限される為、生活保障として国から障害年金を受け取れる可能性があります。ここでは、障害年金の基礎知識について解説したいと思います。
障害年金の基礎知識について
障害年金とは?
障害年金とは、一体どのような年金かご存じでしょうか?まず、年金と聞くと思い浮かぶのは65歳から受給できる老齢年金。また被保険者が亡くなった際に支払われる遺族年金などをイメージしますよね。ですが、20歳以上の方でも受給可能な年金もございます。それが、障害年金です!障害年金は、病気や怪我などで日常生活や就労が制限されている方が対象の公的年金です。しかし、障害年金は制度として、まだまだ認知されておらず、障害年金じたいを知っていたとしても、年金制度が複雑です。自分では必要書類を揃えられないなど、色々とハードルがあって障害年金受給の請求を断念している方は後を絶ちません。しかし、条件を満たしている場合、しっかりと請求すれば受給可能な年金です。ですので、知識を身に着け、この制度を有効的に活用していきましょう。
障害年金の受給者割合
厚生労働省による年金制度基礎調査では、現在、約200万人の方が障害年金を受給されています。内閣府の障害者白書によれば、20歳以上65歳未満の方で障害がある方は約320万人おり、障害年金受給の可能性があるにも関わらず、実際に受給しているのは約6割程度であるのが現状です。もちろん、障害者認定されている方の中には、障害年金受給要件を満たしていない方もおり、また、障害者認定されていなくても受給資格を得ている方もいます。なので、正確な数値とは言えないのですが、現実として貰えるはずのお金を貰えていない方がいると言うのも事実です。
- 初診日要件
障害年金において、初診日は非常に重要なポイントです。初診日とは、障害の原因となった病気やケガに関して、初めて医師による診療を受けた日のことをいいます。また、同一の病気やケガで転院した場合でも、一番はじめに診療を受けた日が初診日になります。
- 制度加入要件
医療機関で診療を受けた初診日において、国民年金や厚生年金などのいずれかの年金制度に加入している必要があります。これに該当しない場合であっても、初診日に20歳未満、または60歳以上65歳未満であれば、年金制度未加入時期の初診日でも、国民年金加入している同等の扱いになります。但し、これは日本国内に本人の住所がある場合に限ります。また、20歳未満の初診日の場合には所得制限があります。
- 保険料納付要件
保険料納付要件とは、初診日の前に決まった月数以上の保険料を納付しているか、または年金の免除を受けていることをいます。具体的には、①初診日の前々月までの年金加入月数3分の2以上が保険料納付済み、または免除されている月である。②初診日の前々月までの一年分が保険料納付済み、または免除を受けた月である。これが要件になります。ただし一年要件においては、初診日において65歳未満であることも必要条件になります。
- 障害状態該当要件
障害状態該当要件とは、障害状態が障害認定日に障害等級表に定められた等級に該当していることです。障害認定日とは、その障害の原因となる病気や怪我における初診日から1年半を経過した日のことをいい、まず最初に、障害の状態を定める日であります。1年半に満たなくとも、症状が固定した場合にそれが障害認定日と認められることもありますのでご注意ください。障害等級には、障害厚生年金の場合、1級、2級、3級と規定があり3級の下には障害手当金がありますが、国民年金に関しては1級と2級のみしかありません。また、障害認定日に障害状態が軽くても、その後状態が重症化した際には障害年金を受給できるケースもあります。
障害年金の請求方法
- 障害認定日請求について
障害認定日請求とは、初診日から1年半経過した日またはそれ以前の治った日以降3ヵ月以内の障害程度について、障害年金を請求することをいいます。ただし、初診日要件などを満たしており、もちろんですが、障害等級に該当していなければなりません。この請求は、大幅に請求時期が遅れたとしても、障害認定日の診断書などを取得できれば最大5年分の年金を受給することが可能となります。
- 事後重症請求について
事後重症請求とは、障害認定日に障害程度が軽度で障害等級に該当しなかった方が、その後症状が悪化し障害等級に該当する状態になった場合、障害年金を請求することをいいます。事後重症請求の場合、年金受給に関しては請求手続きを行った翌月分からになり、遡及して年金を受給することは出来ません。
- 初めて2級の請求について
初めて2級請求とは、既に障害を持っている方がさらに障害を負い、障害を併合して初めて2級に該当する方が請求する方法をいいます。この場合、年金が支給されるのは、請求手続きした月の翌月からということになります。また、初めて2級の初診日要件などは後の傷病のほうで見ますので、ご注意ください。
- 20歳未満の初診による請求について
20歳未満の初診による請求、いわゆる「20歳前傷病」とは、初診日が20歳前の時期にあり、またその時年金制度に一切加入していない方が、20歳到達時に障害基礎年金を請求する制度のことをいいます。請求し2級に認められた場合、障害基礎年金が支払われます。但し、20歳前請求には受給制限(所得制限)があります。
障害等級の法律定義と具体的な内容とは?
- 1級の場合について
法律定義では、身体機能障害、または、長期安静を必要とする病状において、日常生活を不能ならしめる程度に該当します。具体的な内容で言うと、他人の介助無しで日常生活が殆ど出来ない障害状態です。かろうじて身の回りのことが出来るものの、それより高度な活動は出来ない、または、活動を制限されている方、活動範囲が常に自分のベッド周辺に限定される方、このような方は1級相当となります
- 2級の場合について
法律定義では、身体機能障害、または、長期安静を必要とする病状において、日常生活を著しく制限される、または、著しい制限を加えることが必要な程度に該当します。具体的な内容で言うと、必ず他人のサポートを借りる必要は無いが、日常生活を自分で送ることが極めて難しく、働くことで収入を得ることが出来ない障害状態です。例えば、家で軽食を作ることは出来ても、それ以上の重い活動は出来ない方、または、活動を制限されている方、入院や在宅において活動範囲が病院内・家屋内に限定さられる方、このような方は2級相当となります。
- 3級の場合について
法律定義では、傷病が治らない為に働くことに制限がある、または、働くことに制限が必要な方が該当します。具体的な内容で言うと、日常生活で殆ど支障は無くとも、働くことの制限がある方の場合には3級相当となります。
- 障害手当金について
法律定義では、傷病が治った者で働くことに対して制限を受ける、または、働くことの制限が必要な程度に該当します。
障害年金をもらう為のポイントとは?
一番大切なことは請求すること
障害年金を請求する上で一番大切なことは、診断書はもとよりしっかりとした書類を提出することです。障害年金は、原則として国民年金・厚生年金保険障害認定基準を根拠に認定されます。日本年金機構認定医が、診断書など医証を吟味し障害等級に該当すると判断した場合に、障害年金の支給が認められます。なので、障害年金受給要件は医師の診断書が重要なポイントになります。普段の診察だけでは先生がわかりえない病状・日常生活における困難さを、事前に伝えておくことも必要でしょう。そして、診断書を補完する意味でも、病歴・就労状況等申立書に簡潔かつ具体的に日常生活等の状況を記載することが大事です。
障害年金請求時の注意点
初診日において国民年金加入者ならば、障害基礎年金の支給の対象になります。厚生年金保険加入者ならば障害厚生年金が支給の対象になり、2級以上の場合障害基礎年金に上乗せされた形で支給されます。障害等級1級・2級に関しては国民年金と厚生年金に共通しており、障害等級3級・障害手当金に関しては厚生年金保険独自の給付になります。なので、初診日にどの年金制度に加入していたかで、障害年金受給の有無や、受け取る金額がかなり変わってきます。初診日確定後、保険料納付要件を確認し、保険料納付要件を満たさない場合、障害等級該当者であっても受給は出来ないことを覚えておきましょう。請求方法はひとつに限らず、初診日から1年半経過した障害認定日頃の障害状態を認定してもらう障害認定日請求(遡及請求)。現在の症状を認定してもらう事後重症請求。また、初めて2級の請求などさまざまあり、自分がどの請求をするかはケースバイケースです。
障害年金受給金額の目安とは?
障害年金は非課税所得になります。確定申告の必要はありません。受給金額は、初診日に自分が加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金など)や納めた保険料の金額、障害等級の違いで大きく変わり、配偶者や子供など扶養者の有無で金額に差がつくことがあります(加給年金・子の加算など)。例えば、障害基礎年金の場合(令和5年度価格)、金額計算は、1級で795,000円×1.25+子の加算、2級で795,000円+子の加算で計算することが可能です。1級・2級共につく子の加算分として、18歳到達年度の末日を経過していない子がいる、または20歳未満で障害等級1級・2級程度の障害を負った子がいる場合、第2子までは1人228,700円、第3子以降は1人76,200円が加算されます。年金保険料支払い義務のない20歳前に初診日がある場合(20歳前傷病)、所得制限が設けられおり、世帯人数や所得額に応じて2分の1の支給停止・全額支給停止などが設けられています。また、障害厚生年金の場合、1級で報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金、2級で報酬比例の年金額+配偶者の加給年金、3級で報酬比例の年金額(最低保障額596,000円)となります。1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。年金額は、物価や賃金の変動で毎年見直しされて支給額に反映します。
障害年金の手続きは早めに行うことが大事!
障害認定日より5年経過すると受給不可になる
初診日から1年半経過した障害認定日に、一定の障害状態が有る場合には障害年金が受給できる可能性があります。障害認定日の請求は、請求が遅れても最大5年間遡っての受給可能です。これを遡及請求などといいます。しかし、時効消滅が5年ということをご注意ください。例えば、障害認定日から6年目に請求した場合、年金は約5年分しか支給されません。なので、1年分損したことになり、障害基礎年金2級であれば約80万円を受給し損なったとも言えるのです。
障害認定日の診断書が取れなくなる
法的にはカルテ保存期間は5年です。なので、最後の受診から5年経過した場合診断書や受診状況等証明書が取れなくなることがあります。障害認定日の診断書が取れない場合、障害認定日の請求は行うことが出来ず、事後重症請求となるので翌月分からの受給になります。障害基礎年金2級で5年分であれば、約80万円×5年=約400万円を貰い損ねたと考えることもできます。
初診日証明が取れない
医療機関におけるカルテ保存期間は5年ときまっています。なので、最後の受診から5年経過すると診断書や受診状況等証明書(初診証明)がとれません。受診状況等証明書が取れない場合、原則的に障害年金の手続きができなくなり、当然受給できなくなります。こういった場合は、受診状況等の代わりに参考資料や初診日第三者証明を提出することで、初診日が認められる可能性があります。しかし、はじめて障害年金を請求する方には少し難しいかもしれないので、障害年金を専門にしている社会保険労務士などに相談するのもありでしょう。
裁定請求で不支給の場合は?
障害年金を裁定請求するも、思うような結果を得られないことがあります。不支給決定通知書が届いたり、障害厚生年金などの場合、2級相当の状態と自覚しつつも3級で着地することなどありえます。結果に納得がいかない場合には、審査請求・(再)審査請求など不服申し立てを行うことも可能です。これは裁定請求したものを、社会保険審査官及び社会保険審査会に申し立てて再度審査してもらうものなのですが、確率的にかなりハードルが高いと言われています。なので、不服申し立てが厳しいとなれば、新たに診断書を取得し請求する再裁定請求や時期を見て額改定請求などに方向転換することもありでしょう。また、審査請求などを進めつつ同時に再裁定請求を行うことも可能です。このへんも非常に難しいはなしですので、障害年金を専門としている社会保険労務士に相談してみるのもありでしょう。
まとめ
ここまで、障害年金の基礎知識について簡単に解説してきましたが、制度の仕組みなどはおわかりいただけたでしょうか。障害年金は初診日に国民年金または厚生年金に加入し、年金保険料滞納せず支払っている(あるいは免除している)ことが最低限の条件となります。また、障害年金とは別に、障害者手帳などの取得により、医療費助成・税控除・公共料金割引などの優遇措置を受けることも可能です。障害をお持ちの方々が、より安心で生き生きした人生を送れるよう、あらゆる制度のご活用をお勧めいたします。